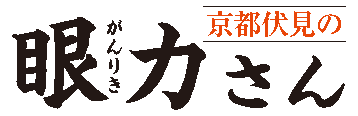残暑が厳しい9月はTシャツ一枚で十分です。
秋は七草を数えながら

朝晩に秋の訪れを感じる9月上旬、草木の先に白く光る朝露を見かけることから二十四節気では白露(はくろ)と呼びます。この時期は一年で最も台風が多く発生し、稲荷山は通行規制が出ることもあります。お詣りの際は情報を調べた上でご参拝をお勧めします。
稲荷山は標高233メートルあることから参道脇には複数種の山野草が見られ、萩、ススキ、クズなどの秋の七草も混じっています。秋の七草は春の七草がゆと違って、煎じて薬にする生薬が主で、他に桔梗、おみなえし、撫子、藤袴がありますがこの4種類はお山で自生のものは見られません。
眼力さんの常連さんからメールを頂戴しました

伏見稲荷にお参りは三の峰、眼力社にお参りした後に、青山たばこ店に必ず寄ります。 土産物、ビ一ル、スイ一ツ沢山の飲食類があり店内に座る場所もあり、店の女将さんと会話するのが楽しみです。歴史のあるお店で、伏見稲荷のこと含め、色々なことを教えて頂けます。名物女将さんです。お参りの帰りに立ち寄る方や外国人の方いつも沢山の方でお店はいっぱいです。是非一度立ち寄ってみて下さい。
株式会社ユアサ上野祥弘 様
無病息災を願う重陽の節句

9月9日は五節句のひとつ、重陽の節句です。この日は菊の節句とも呼ばれ、菊酒を飲んだり栗ご飯を食べたりして無病息災、長寿を祈ります。関西では枚方菊人形など菊をテーマにしたイベントがありましたが近年では時代とともになくなり、秋に菊を愛でる風習やこの節句自体を知らない人も多くなって来ています。
またこの日は9日であることから「くんち」と呼ばれ秋の収穫を祝う日でもあります。九州では長崎くんちや唐津くんちが有名ですがこの名残だそうです。
昔からこの時期は秋の実りに感謝し、作物を体に取り込んで自然と一体化しようとした歴史が感じられます。伏見稲荷は五穀豊穣、稲の神様ですからこの時期はこちらにお礼を伝えに行けば生涯食べることには困らないでしょう。
先祖に感謝し新しい半年を始める秋分。
9月も半ばを過ぎると、テレビCMやイベントなど秋の雰囲気が漂ってきます。と言ってもここ数年は残暑が長引き、早く涼しくなってくれないかなぁと祈るばかりで、この時期は本来何をすべきかを私たちは忘れがちです。
毎年、9月20日を過ぎれば秋分を迎えます。秋分は昼と夜の長さが同じになり、そこから少しづつ夜の方が長くなっていく境目の日になります。昔から遥か彼方の西にある極楽浄土と現世がもっとも近くなる日と言われ、あの世に先だった先祖を偲んで感謝する日とされて来ました。
常日頃から神様に手を合わせる習慣はあっても先祖を無視するのは良くありません。この時期はお墓参りをきちんとしてから、神社にも手を合わせるようにしたいものです。
「おはぎ」と「ぼたもち」の違い

お彼岸の日に墓前や仏壇にお供えされるおはぎ。ぼたもちとも言いますがその違いをご存知でしょうか?お彼岸は春と秋にありますが、秋には萩が、春には牡丹が咲くのでその名にちなんでこのように呼ばれるようになっただけで、実際は全く同じものを指します。
古風な店先が人気の熊鷹社前。
稲荷山に登りなれた人が言うには「観光は千本鳥居まで信仰は頂上まで」。ここ、熊鷹社は観光で訪れた人の次の分岐点と言ってもいいかもしれません。三差路に開けた熊鷹社前は大きな池もあり右手に行けばたくさんのお塚が、左手に行けば頂上にたどり着きます。ベンチもお茶屋さんもあるのでここで一息入れる人も少なくありません。
 ●9月下旬 平日午前9時ごろの熊鷹社前
●9月下旬 平日午前9時ごろの熊鷹社前
9月の京都は残暑が厳しく蒸し暑い日も多いですが稲荷山は標高があるため少し涼しく秋めいてきます。初めて訪れる人でもTシャツ一枚で上り下りできるので楽です。日照りの強い日はタオルを一枚首にかけておくことをお勧めします。
秋晴れの日は雅な色合いの写真が撮れるので、日本的な建造物や自然の風景を撮影している外国人に出会います。

平日の午前9時の拝殿ですがこんなにもたくさんの観光客が訪れていました。この時期は気候が良いので修学旅行生が多いようです。

この写真は参道から少し外れた神寶神社への坂道から鳥居を見下ろしたもの。中をたくさんの人が歩いているのが見えます。鳥居の数も人の数もこの世に存在する願いごとの多さを物語っています。

熊鷹社を右手に曲がるとたくさんのお塚があります。その間から下をのぞくと木立の間から参道と鳥居が見えます。スピリチュアルな人が言うにはこの辺りは神域にあたり、観光で撮影を楽しむ人が多いのは結構なのですが、しっかり神様に見られているエリアなので失礼のないようにお気を付けくださいとのことです。
眼力さんに到着しました。

稲荷山が台風の被害に見舞われ二週間もの間、入山規制されていたのは2018年のことでした。その後は大きな災害もなく月参りの参拝者も観光客も戻ってきています。そんな過去を知りつつも、狐の手水は何事もなかったように涼しい顔で冷たい水を流しています。

帰りには秋空の下、表参道でたくさんの修学旅行生が記念撮影をしていました。正午から14時までは食事時のため境内の飲食店も屋台も観光客であふれかえっています。少しでも空いているお店に行きたい人は伏見稲荷大社の敷地から出た、JR沿線や京阪沿線の飲食店をお勧めします。ラーメン、喫茶、鰻専門店などがあります。